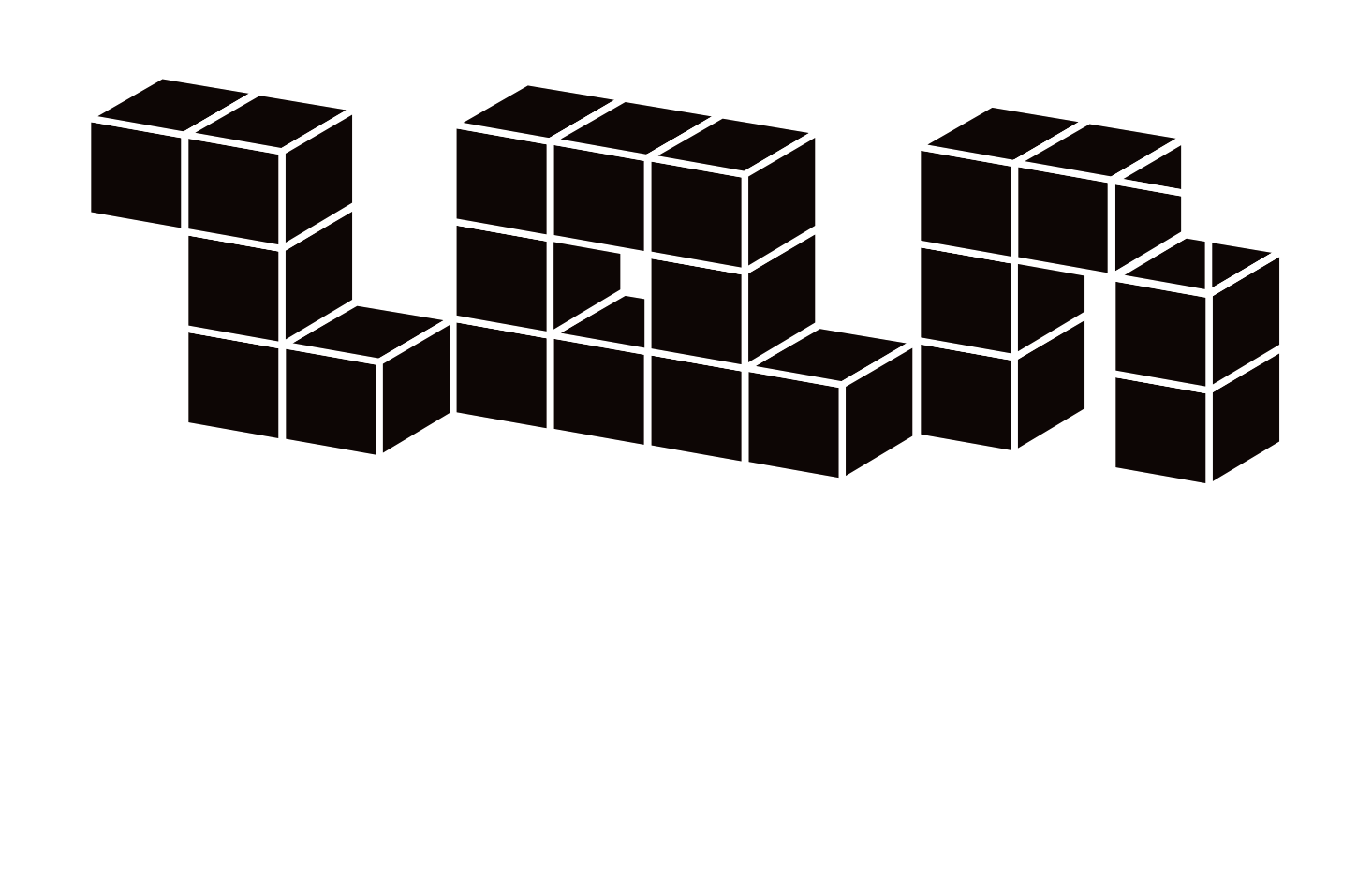なぜか仕事は、いつも締め切りギリギリ…
「1週間の猶予があるこのタスク、余裕だな」と思っていたのに、気づけば締め切り当日の朝。慌ててコーヒーを流し込み、猛烈な勢いでキーボードを叩いている…。
そんな経験、ありませんか?その現象には、ちゃんとした名前があるんです。
その現象の名は…
パーキンソンの法則
“仕事の量は、完成のために与えられた
時間をすべて満たすまで膨張する“
Work expands so as to fill the time available for its completion.
もし、締め切りが違ったら?
同じ「資料作成」で比べてみよう
Case 1: 締め切りは1週間後
時間はたっぷり。最高の資料を作ろう!…と意気込むが…
結果:7日間という時間をすべて使い切ってしまった。
Case 2: 締め切りは3時間後
時間がない!やるべきことだけに集中だ!
結果:3時間で本質を押さえた資料が完成した。
なぜ仕事は”膨張”するのか?
時間のスキマを埋める「3つの心理」
完璧主義のワナ
「時間があるなら、もっと良くできるはず」と考え、本質的でない細部にこだわり始めてしまう。
心理的な安心感
「締め切りはまだ先だ」という安心感が、無意識のうちに緊張感を緩め、作業ペースを落とさせてしまう。
無意識のペース調整
マラソン選手がゴールまでの距離でペースを調整するように、締め切りまでの時間で無意識に作業量を調整してしまう。
【豆知識】元々は役所の”不思議”を説明した法則
この法則は1955年、英国の歴史学者シリル・パーキンソンが提唱しました。彼は、英国の役所で「仕事の量に関わらず職員の数が増え続ける」現象を観察し、その非効率性を皮肉を込めて指摘したのです。組織や人間の性質を鋭く突いたこの法則は、今や仕事術の古典として知られています。
法則を知って、時間を支配する
今日からできる3つの方法
自分で「締め切り」を創る
「1週間で資料作成」を「月曜:構成案」「火曜:データ収集」のように細かく分け、それぞれに短い締め切りを設定します。大きな山も一歩ずつなら登れます。
時間を「箱」に入れる (タイムボクシング)
「このメール返信は15分」「このタスクは25分」と、作業に制限時間を設けます。タイマーをセットして、ゲーム感覚で集中しましょう。
やることを「具体的に」する
「資料を作る」という曖昧なタスクは先延ばしの元。「競合A社のデータを集めてグラフにする」まで具体化すれば、すぐに行動に移せます。
✨ AIでタスクを具体化してみよう
「やることを具体的にする」をAIがお手伝い。曖昧なタスクを入力すると、具体的なステップに分解します。
注意:万能の法則ではありません
これは経験則であり、風刺です。新しいアイデアを出すなど、じっくり時間をかけることで質が高まる創造的な仕事もあります。目的によって、時間の使い方を使い分けることが重要です。
あなたは時間の主人になれる
パーキンソンの法則は、私たちを縛る呪文ではありません。
その仕組みを知り、AIのようなツールも活用することで、私たちは時間を意識し、コントロールすることができます。
明日から、時間に追われるのではなく、時間を使いこなしてみませんか?